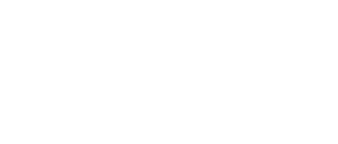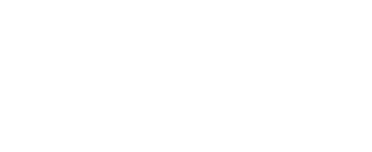写真右から:
三菱商事パッケージング株式会社 コーポレートスタッフ本部 人事総務部 棚橋里江 様
三菱商事パッケージング株式会社 コーポレートスタッフ本部 人事総務部 主査 増田直希 様
三菱商事パッケージング株式会社 執行役員 コーポレートスタッフ本部 人事総務部長 石橋伸太 様
東急不動産株式会社 都市事業ユニット 都市事業本部 ビル運営事業部 阿部純子
多くの企業が注目している健康経営。その実現には様々な視点からの取り組みが必要となりますが、とりわけ社員の健康・余暇・成長をサポートする福利厚生の充実は欠かせない代表例の一つとして挙げられます。
今回は、株式会社イーウェル※1 が提供する福利厚生サービス「WELBOX(ウェルボックス)」を導入された、三菱商事パッケージング株式会社様(以下、三菱商事パッケージング様)における、健康経営推進の取り組みをご紹介します。
三菱商事パッケージング様で、健康経営施策全般を推進し、健康経営優良法人※2 の取得・維持を支える、執行役員人事総務部長の石橋伸太様(以下、石橋様)と同部の増田様、棚橋様に、実践の軌跡や具体的な効果などをお聞きしました。
- ※1:東急不動産ホールディングスグループ企業。福利厚生・健康支援サービスの開発・運営を提供。
- ※2:健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している法人を可視化・顕彰する制度です。「健康経営優良法人」に認定されると「健康経営優良法人」ロゴマーク使用の他、従業員や求職者・関係企業などからの評価や自治体や金融機関等において様々なインセンティブが受けられます。
なぜ“健康経営”に注力するのか?三菱商事パッケージング様が取り組む原点とは
企業として、健康経営に取り組み始めたきっかけを教えてください。
石橋様:世間的にも働き方改革というワードが出てくるようになってきた2017年ごろから、当社人事部内においても「社員の健康増進に加え、組織の活性化や会社の持続的な成長等を目的に各種施策の検討を進める必要があるのではないか」という機運が高まりました。そこで、手探りながら様々な施策を考え、中長期的な計画を策定し、働き方改革と健康経営の両輪で取り組む方針を決めたことがきっかけです。
当社は社員が健康的かつイキイキと働ける職場環境の形成を目指し、多様な働き方ができる仕組みを整えることで、社員の健康に加え、生産性向上にも寄与できると考え、働き方改革とともに健康経営を重視しています。

当時はまだ健康経営という言葉も浸透していなかった時期ですが、なぜ働き方改革とあわせて推進されたのでしょうか?
石橋様:計画を策定していた時期、働き方改革を実行し、いち早く成果を上げ注目されていた、某メーカー様のワークショップに参加しました。そこでは働く場所や時間の選択肢を広げることで、仕事へのモチベーション向上にも繋がっており、また社員の「イキイキ」や「ワクワク」を喚起する取り組みもあわせて紹介されていました。これをヒントに当社でも、働き方改革にあわせて健康経営を推進する方向に定めていきました。また、コロナ禍において社員の健康を守ると同時にビジネスを継続するための働き方が求められましたので、この動きをさらに加速させました。
貴社のコーポレートサイトでは健康経営に関する様々な指標と実績が公開されていますが、特に高い目標を掲げられている有給休暇取得率は達成されつつあります。現時点のご進捗状況を教えてください。
増田様:昨年度(2024年3月末)の着地は68.9%。今年度は2月末時点で約63%です。年度末までの残り約1ヶ月は社員の駆け込みで需要が集中する時期でもありますので、急速に伸びる傾向があります。目標達成に向けて社内周知する等、追い込みをかけています。

有給休暇取得率だけがゴールではない!“多様な休み方”がもたらす健康と生産性
有給休暇取得率を高めるため、どのような工夫をされているのでしょうか?
棚橋様:メール配信・オフィス内のポスター掲示・社内報など、社員に向けた発信は力を入れています。また、有給休暇中に福利厚生サービスを利用した社員への協力を仰ぎ、インタビュー記事を作成して社内で配信や掲示をする工夫もしています。このように休暇取得に前向きになれるようなアプローチを継続的に行っています。
増田様:有給休暇取得率の目標値を設定していますが、当社では柔軟な働き方の選択肢として、フレックス制度や特別休暇なども複数用意しています。これらは当然ながら有給休暇ではありませんので、有給休暇取得率が上がらない要因に繋がります。しかし、少し勤務時間をずらしてリフレッシュしたい、育児や介護のために休みたい、などの多様なニーズがありますので、それらを含め社員が柔軟な働き方を選択する中で、自然に有給休暇を取得しやすい環境を整備しています。
石橋様:有給休暇取得率も大事な指標ですが、それ以外も含めて健康経営の視点で社員がイキイキと働けているかどうか、生産性に与える効果などを評価していく必要があると考えています。

「サービスがあるのは嬉しいが使わない」が大多数だった福利厚生サービスの知られざる実態とは?
改めてテーマを健康経営に戻しますが、これまでに健康経営を推進されてきたなかでの課題などはありましたか?
石橋様:健康経営を推進するにあたり、福利厚生の見直しは必要であると考えていました。実はWELBOXを導入する以前から同類の福利厚生サービスは導入していたのですが、社員の利用率は低迷していました。
増田様:前サービスでは、WEBページやアプリのログイン率が、社員数に対して約10%程度であり、福利厚生が利用される回数も数えられる程度でした。もちろん、全社員への周知やセミナーを開催するなど試行錯誤はしましたが、長年、利用率が低迷しているのが現実でした。そこで思い切って、福利厚生サービスの切り替えを検討する運びになりました。
棚橋様:他の福利厚生サービスを検討するにあたり社内アンケートを実施したのですが、「サービスがなくなるのは困る」「サービス自体はあれば嬉しい」という回答が多いのには驚かされました。つまり、「本当は使いたかったけど、使えていなかった」という実態が浮き彫りになったのです。このようなタイミングで出会ったサービスがWELBOXでした。

WELBOXへの福利厚生サービスの切り替えに際して、苦労されたことはありましたか?
増田様:単にサービスを入れ替えて終わりではなく、当社の健康経営・福利厚生の制度全体を活性化させることに繋げたいと考えていましたので、どのような仕組みや建付けで会社にプレゼンテーションし、社内導入を実現するかについて検討を重ね、労力をかけました。
石橋様:あくまでも福利厚生サービスの利用率を上げることが目的ではなく、健康経営優良法人として相応しい「職場作り」、ひいては「社員がイキイキと活躍できる職場作り」のために、システムを見直す必要がある旨を多くの関係者と話し合い、合意に至りました。さらに有給休暇取得率の目標を必ず達成したいという我々の思いも強いメッセージとして伝わり、承諾を得ることができたと考えています。
WELBOXへの福利厚生サービス切り替えによる変化
WELBOXの導入後は、どのような変化が見られましたか?
増田様:WEBページやアプリの操作性(UI/UX)が格段に良くなり、使いやすくなったことを真っ先に実感しました。結果として、社員のログイン率は約80%に、利用率も約50%に上昇しました。また、前サービスで利用率やログイン率を知るには、問い合わせが必要でしたが、WELBOXでは管理者アカウントからリアルタイムに閲覧できるようになった点も大きな変化と言えます。
棚橋様:WELBOXは特典面でも充実していますね。例えばポイント施策(EC経由での購入にともなう特典等)は、社員にも人気があります。正直にお話をすると、前サービスは利用を促す立場の担当もあまり使いこなせていなかったのですが、WELBOXは社員全員が楽しく使えています。
増田様:WELBOXから利用促進を目的とした紙の冊子が定期的に発行され、社員に配布していますが、中を開くとクーポンや新しい特典の情報などが満載になっています。同じような情報はWEBページやアプリでも確認できますが、紙の冊子ならではの見る楽しさがあり、社員同士のコミュニケーションも生まれています。このように職場の雰囲気にも変化が見られています。
年々厳しさが増す、健康経営優良法人の認定を維持するためのPDCAとは?
最後に健康経営に関して、新たな課題や、今後さらに強化される取り組みがあれば教えてください。
石橋様:当社は、2020年より連続して健康経営優良法人の認定を取得していますが、この認定を更新するための審査は、年を追うごとに厳しくなっています。毎年、取り組みを継続するだけでなく、認定の際にフィードバックされた課題を改善するPDCAを回していかなければ、今後の維持は難しくなると考えています。
有給休暇取得率をはじめ、時間外勤務時間、育児休業取得率など様々な指標の改善はマストですが、何よりも従業員満足度を高めるアクションを起こして、社内外から選ばれる会社で在り続けることが大切だと感じています。

具体的な取り組みとして、四半期に1回の健康経営を可視化する調査(ウェルビーイングに特化したサーベイ)や、隔年ごとに組織風土調査を実施しています。なかなか見えづらい社内の実態をスコアリングして定点観測をしながら、社員との最適なコミュニケーションを図り、改善に取り組んでいきたいと考えています。
- ※掲載内容は2025年2月取材時のものです。
ご利用サービスの紹介
福利厚生サービス「WELBOX(ウェルボックス)」

「WELBOX(ウェルボックス)」は、株式会社イーウェル(東急不動産ホールディングスグループ企業)が提供する福利厚生サービスです。
趣味や“じぶん時間”の充実はもちろん、介護や育児の両立支援まで、ワーカーとそのご家族の暮らしや健康に役立つメニューが満載!
様々なメニューを会員価格で利用でき、従業員の満足度向上や「こころ」と「からだ」の健康促進をお手伝いします。